文系の大学院進学は、進路に悩む大学生にとって、大きな選択肢の一つ。しかし、「GPAが低いと無理?」「文系院生ってどんな生活?」「就活に不利?」といった疑問や不安も尽きません。
そこで、慶應義塾大学経済学研究科と、文学研究科の在校生にインタビューを行い、入試制度から就職活動、そして気になる院生生活のリアルまで、語っていただきました。
Mさん:慶應義塾大学経済学研究科2年
Sさん:慶應義塾大学経済学研究科2年
Lさん:慶應義塾大学文学研究科2年
大学院進学のきっかけ:大学院進学から広がる、キャリアの可能性
大学院進学を意識した時期はいつですか?
Mさん(経済):経済学系のインターンを始めたのは、大学2年生の12月頃でした。そこで働く中で経済系の研究職の方々と話す機会があり、だんだんと大学院進学を意識するようになりました。3年生になる頃には進学を考え始め、就職活動も少しだけやりましたが、最終的には大学院に進むことにしました。
Sさん(経済):私が進学を決めたきっかけは、学部1〜2年生の頃にデータサイエンスや統計に興味を持って勉強していたことです。3年生になった頃には就活も考えていましたが、理系の大学院生と競うには専門性の面で不安がありました。そこで、自分も大学院に進学することで専門性を身につけようと決めました。その後は統計よりもマクロ経済学に関心が移り、将来はアカデミアでのキャリアも視野に入れるようになりました。研究を進める中で、教員との距離も近くなり、研究の厳密性や指導の細かさが学部時代とは全く違うことを実感しました。
大学院の入試について:GPA1.7でも進学できる?入試制度と合格の鍵
経済学研究科の入試はどのようなものなのでしょうか?
Mさん(経済):慶應の経済学研究科には、第一期入試と第二期入試という2つの入試方式があります。第一期入試では、一次試験が筆記試験、二次試験が口頭試問(面接)です。第二期入試では、一次試験が論文審査、二次試験が面接となっています。私は第二期入試を選び、論文審査で受験しました。第二期入試の出願は大学4年生の12月で、それまでに卒業論文を早めに仕上げて提出しました。一次審査の合格通知が来たのは1月の後半から2月初めくらいで、2月末に面接があり、その日のうちに合格が出ました。2月23日から25日あたりに進路が確定し、慶應の経済学研究科に進学することになりました。
院入試にはGPAが必要になってくるのでしょうか?
Mさん(経済):結論必要です。GPAが一定以上あれば第一期入試の一次試験が免除になる制度があり、成績が良い人はその制度を使って面接のみで受験するケースもあります。私はGPAがあまり高くなかったので、その制度は使えませんでした。東大の大学院入試も夏頃に受けました。一応勉強はしましたが、あまりうまくいかずに不合格となりました。その後は慶應一本に絞って、卒論をしっかりと書き上げました。ちなみに、GPAが低くても慶應の大学院には進学可能です。実際、私の最終的なGPAは1.7くらいでした。
Sさん(経済):GPAが高いと、学部在学中に「先取り科目」と呼ばれる大学院科目を先取り履修できる制度がありました。これはかなり助かりました。大学院進学後の履修が分散でき、研究に集中する時間を確保しやすくなります。 大学院に入ると、必修科目はありませんが、「コア科目」と呼ばれる実質的な必修のような授業があります。これらは毎週課題が出るなど、かなり負荷が重くなります。そのため、先取りしておけるとかなり楽になります。
院に進学するにあたってゼミ選びは重要ですか?
Mさん(経済):ゼミ選びも非常に重要です。飲み会ばかりの「飲みゼミ」に入ってしまうと、研究に真剣に取り組むのが難しくなることもあります。先生にもいくつかタイプがあり、研究に熱心な人もいれば、教育にはあまり力を入れない人もいます。ゼミの雰囲気は進学後の研究生活に大きく影響します。また、ゼミに入っていない場合でも、「The Professional Career Program(PCP)」のような形で、個別に教員と研究を進める制度があります。その先生が指導教員になってくれることもあるので、しっかりとした関係性を築いておくことが大切です。 さらには、推薦状が必要な場合も多く、内部進学であっても、基本的には指導教員から出してもらうことになります。日頃から研究テーマを相談したり、論文を読んでもらったりして信頼関係を築いておくとスムーズです。
Sさん(経済):研究者志望であれば、ゼミの選び方や指導教員との関係性が非常に重要になります。推薦状が必要になることも多いため、ゼミで信頼できる先生と出会えることはとても大切です。
学部時代どのように単位を取っていましたか?
Mさん(経済):2年生の時点で教養科目の単位はほぼ取り終えていて、残りは興味のある授業を楽しんで受けていました。課題提出が少ない授業も多く、レポート一本で単位がもらえるようなものもありました。もちろん、落としたくなかったので最低限はこなしていました。一方で、必要な単位のためにあまり興味のない授業も履修しなければならず、出席だけしてD評価で終わるようなこともありました。周囲から「何でそんな成績なの?」と言われることもありましたが、実際には単にやる気がなかっただけという感じです。言い訳としては、経済系の科目は比較的成績が良かったです。特に金融系の科目は高得点で揃えていましたし、計量経済学の授業はS評価でした。自分の関心がある分野では比較的好成績でした。興味のある科目だけ成績が良かったりするのは院生あるあるです(笑)
院入試に向けて準備しておくことはありますか?
Mさん(経済):大学院入試に向けて特別に意識していたこととしては、やはり卒論を頑張って書くということが一番大事でした。卒論を通して「自分が何をやってきて、何をやりたいのか」が明確になります。学部の卒論レベルでは内容の完成度よりも、研究の「やり方」を学ぶことの方が重要だと思います。
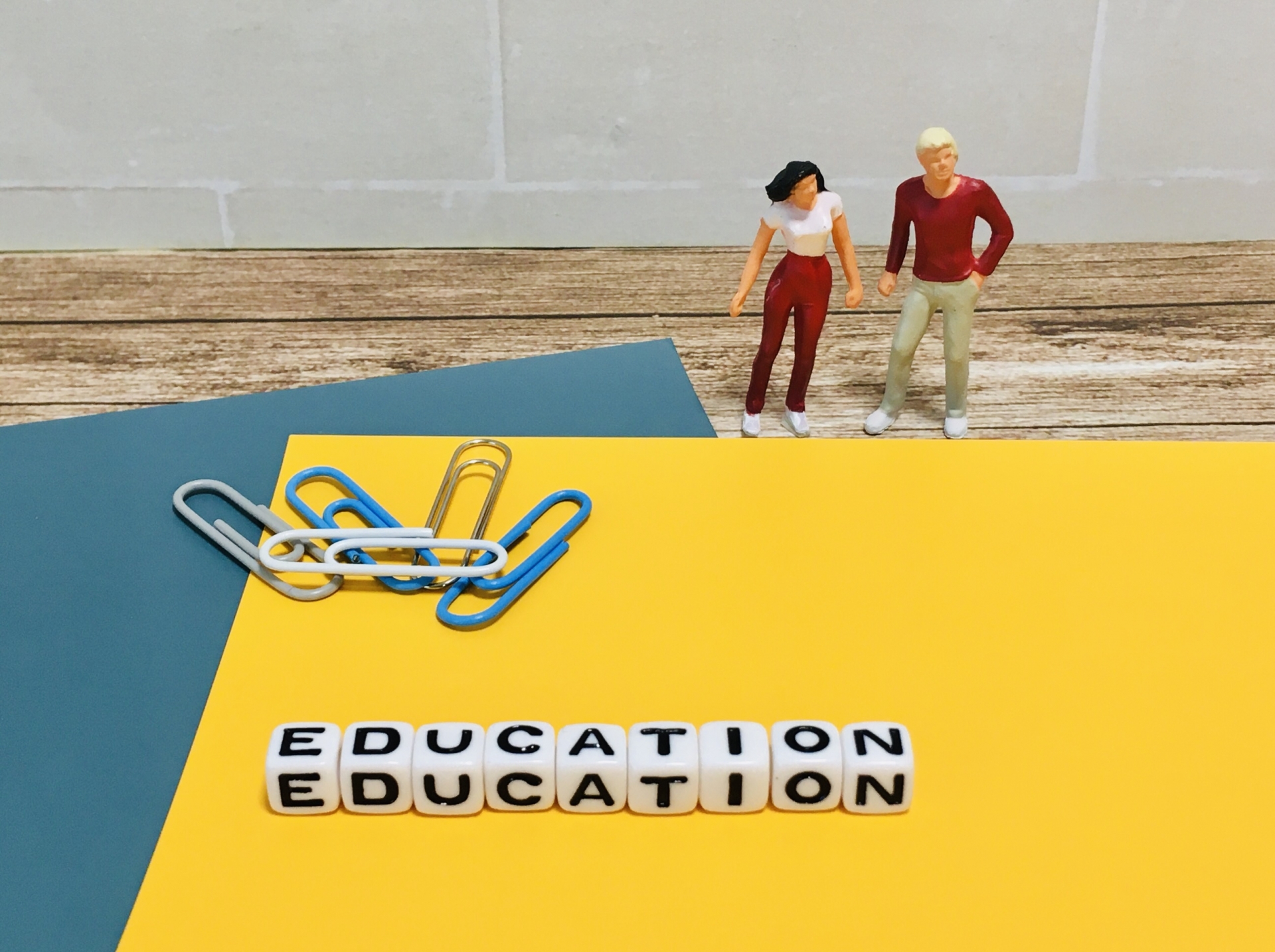
大学院での生活について:大学よりも自由!?リアルな研究生活とは
院生の生活はどのようなものですか?
Mさん(経済):大学院生活はかなり自由で、自分の机が与えられ、基本的には自習が中心になります。理系と違って、文系院生には「この時間に必ず研究室にいないといけない」といったコアタイムは基本的にありません。自分でスケジュールを立てて、自分のペースで進められますし、研究さえ進めば誰にも文句は言われません。成果(修士論文)さえ出せばよくて、その過程はそれほど重視されませんね。 もちろん、サボっていては良い論文は書けないので、結果としてみんな自発的に頑張っています。実際、サボっている人はほとんど見かけませんし、サボっても結局自分に返ってくるだけです。自己管理が重要になります。朝は遅めに起きて、気分次第で大学に行くか家で作業するかを決める。毎日天気が良ければ登校し、悪ければ自宅で作業するような感じです。大学に行った日は、自分のデスクでひたすら論文を読んだり、課題をこなしたりします。たまに同じ研究科の仲間と「昼飯でも行くか」と声をかけ合って一緒にご飯を食べたり、研究の話をしたりして、それぞれまた作業に戻るような毎日です。授業はライブ感のある講義も多く、研究者の話を90分聞くだけの授業でも学びが多くあります。もちろん、厳しい授業もありますが、楽なものは本当に楽です。
Sさん(経済):僕もそう思います。生活面でいえば、大学院は思っている以上に自由で、楽しいと思います。理系のように毎日研究室に詰めるようなこともなく、パソコンがあれば自宅でも十分に作業できます。私は印刷して論文を読むのが好きなので、大学に来ることも多いですが、正直なところ、大学に来る必要があまりない人も多いです。また、慶應の経済学研究科は人数も比較的多く、専攻する分野も多様です。マクロ、ミクロ、計量経済などでコア科目が共通しているため、課題も多く、自然と助け合うような文化があります。仲間ができやすい環境だと思います。
Lさん(文):研究のモチベーションが上がらない時は、本当に何も進まなくて、自分が社会から取り残されたような気持ちになることもあります。これは浪人時代の「何者でもない感覚」に近いですね。逆に、自制できるようになれば、とても充実した時間を過ごせるようになります。文系の大学院生は数が少ないため、サークルやゼミなどでのつながりが貴重です。特に経済学研究科は人数も多く、専攻もバラバラなので、自然と課題を助け合ったり、研究の進捗を共有したりする文化が生まれやすいです。一方で、文学系の研究科では、同じゼミでも修士・博士合わせて数人ということも多く、孤独感が強いと聞きます。だからこそ、気軽に相談できる仲間を数人でも持っておくことがすごく大切です。
留年することはありますか?
Mさん(経済):大学院では、修士1年から2年に上がる際に留年は基本的にありません。ですが、修士2年で修論が書けなければ、そのまま進級できないことになります。慶應では、修士2年の終わりに「予備審査」があり、そこでつまずくと結果的に留年になることもあります。
大学院に進学して良かったことはありますか?
Sさん(経済):大学院に進学してよかったかと聞かれると、現時点では「楽しい」とは思っているものの、今後の人生にとってプラスかどうかはまだわかりません。ただ、修士課程に関しては、「とりあえず進んでみる」くらいの気持ちでも十分アリだと思います。この経験が将来のキャリアにどう影響するかは、まだはっきりとは分かりません。それでも、修士課程であれば、あまり深く考えすぎずに進んでみるのもありだと思います。「なんとなく面白そうだから」「マスター(修士課程修了)って響きがかっこいいから」くらいの理由でも十分です。実際、進学の動機が明確でなかった人も多くいますし、入ってからしっかり学べば問題ありません。最近では、学部在学中に休学して、時間を取って将来を見据える学生も増えています。そうした選択肢と同じように、「とりあえず修士まで行ってみる」という進路も自然なものだと思います。修士課程は専門性を身につける学位であり、「とにかく勉強したい」「ちょっと違う世界を見てみたい」という気持ちで入る人もたくさんいます。
Mさん(経済):最終的には、「入って良かったと思います」と言えます。少なくとも、修士課程を経験することで得られる自由さや学びの深さは、学部時代には得られなかったものですし、それが自分の成長につながっていると実感できています。

大学院生の就活について:修士号は武器になる?文系院からの就活の強み
院生の就活事情を教えてください
Mさん(経済):就職活動については、修士課程に進んだことが不利になることは全くありません。むしろ、専門職や研究職を目指す場合には修士号が必須のケースも多く、むしろプラスになります。私自身も金融系の専門職で内定を得ましたし、企業によっては「修士以上」が応募条件になっているところもありました。サマーインターンに参加したときも、10人中8人が修士か博士課程の学生で、修士以上でないと応募できない職種も多くありました。たとえばBCGのデータサイエンス職なども修士以上が条件だったりします。つまり、大学院進学がキャリアの選択肢を広げてくれるのは間違いありません。また、文系の大学院生は少ない分、就活で「おっ」と注目されることもあります。面接官にとっても、「文系で院まで行ってるんだ。ちゃんと勉強してきたんだな」と興味を持ってもらいやすいです。
Sさん(経済):私自身は、将来的にはPhD(博士課程)に進みたいという思いもあります。ただ、リスクヘッジとして修士で就活をして内定をもらい、どちらにも進めるようにしています。
今後のキャリアパスについてどのようにお考えですか?
Sさん(経済):今後の目標としては、海外の博士課程への留学を目指しています。海外では博士号の取得がキャリアの条件となる場面も多く、そのためにも今の修士課程でしっかりと準備を進めています。海外の博士課程は一般的に5〜6年かかります。卒業後は大学で教員になるか、国際機関に就職するか、企業に進むかなど、さまざまな道があります。まだその先のことは決めていませんが、まずは海外留学に向けて準備をしています。
Mさん(経済):経済学では「CEMS」という交換留学制度があり、1年間のプログラムでLSEやコーネル大学などに留学し、ダブルディグリー(経済と経営など)の取得も可能になっています。実際に先輩が行ったりすると、後輩もそれに続くことが多いです。経済学の場合、アメリカのPhDは修士課程が一体化していて、通常は5年間の一貫教育です。日本から行く場合は、修士2年を終えてから海外PhDに出願するのが一般的です。
Lさん(文):文学の世界では、博士課程在学中に博士号を取得することは非常に難しく、指導教員でも修士号しか持っていないこともあります。文学では純然と何を書くかが評価されるというよりは、「どこの誰が書いたか」という徒弟制度的な名残が近年まで残っていたように感じられます。今も長年の研究業績の蓄積が求められることもあり、少々複雑です。博士号取得までに10年以上かかることも珍しくありません。このように、分野ごとに進学の事情は大きく異なるので、自分の専門領域ではどのような進路が一般的かをよく調べる必要があります。
さいごに
大学院に進学する意義とはなんでしょうか?
Lさん(文):日本では学歴社会とよく言われますが、ここでいう「学歴」は「学校歴(どこの大学か)」のことです。しかし、海外では学士、修士、博士といった「学位(ディグリー)」が重視されます。海外で働きたい人にとって、修士課程は必須と言えるでしょう。また、就職してから大学院に戻る「リカレント教育」も、最近は注目されています。ただ、多くの修士課程の学生は、心のどこかで博士課程への憧れを持っているように感じます。「行けるなら行きたい」が口癖になるのもそのせいです。
 塾生情報局
塾生情報局 
